直母はミルクや搾乳より楽
赤ちゃんがおっぱいをちゃんと飲めないことに悩んでいる方は意外にたくさんいらっしゃるようです。
私の赤ちゃんは逆子だったので、帝王切開で出産予定日より早く生まれました。
生まれたばかりの赤ちゃんの口は小さく、吸う力も弱かったので、おっぱいから母乳を直接飲むこと(直母とよばれています)はできませんでした。

哺乳瓶で飲む量もなかなか増えず、当時はかなり心配になりました。
しかし、練習をかさねたところ2ヶ月で直母で飲むことができるようになりました。
そこで、半ミにまでこぎつけた経緯をいくつかの記事にまとめました。

この記事はそのダイジェスト版です。
※画像の一部は楽天サイトへのリンクとなっています。
私が直母を追究した理由

当初、私が直母を追求した理由は、たんにやってみたかったからでした。
直母ができるようになると、搾乳をせずにすごせますし、好きな時にあげられるので、色々と楽だと感じました。
そして、1番のメリットは、安心して育児できるということでした。
直母の準備は大きく分けて2つ
哺乳瓶で授乳をはじめて、途中から直母でも授乳する場合、大きく分けて2つの準備をすることになります。
- 途中で直母にきりかえるための準備
-
- 母親が母乳量を増やしていくこと
- 赤ちゃんが直母の訓練をすること
この2つを、簡単に説明します。
母乳の量を増やすための取り組み

まず取り組むべきことといえば、母乳量を増やすための搾乳です。
出産した直後から母乳をおっぱいの外に出し続けないと、母乳をつくる能力は高まっていきません。
出産してから1ヶ月、おっぱいの中の母乳を出さずにいると、母乳をつくる能力はほとんど失われます。

搾乳を始めるタイミングは早いほど有利。
搾乳をたくさん行い、少しでも能力を温存しておけば後で母乳量は増える
私の場合、搾乳をがんばっても母乳量はあまり増えていきませんでした。
それでも直母が始まるとそれなりに増えました。

出産から2ヶ月後は搾乳1回で70mlだったのが、12ヶ月後は130mlに。
入院中から搾乳をなるべくたくさん行って、母乳をつくる能力を高めたり温存したりしていく必要があります。
母乳量を増やすために参考になった書籍
「ちょっと理系な育児」という本は、WHOガイドライン「乳幼児の栄養法」を翻訳してわかりやすく説明しています。
赤ちゃんの母乳育児に関して、少し理系的な解説がされていて、出産前に考えを整理するためにおすすめです。
この本を読むと、誰でも直母はできるようになるし、入院中に直母できなくとも搾乳をたくさんすべきであるということがわかります。
入院中に直母練習はなかなかさせてもらえないことがある
入院中に赤ちゃんと触れ合うことのできる時間は限られています。
入院中にはなかなか直母ができません。
しかも、帝王切開での出産の場合は、入院日数が長くなります。

私の場合、入院中に直母を全くさせてもらえませんでした。
入院中の搾乳はできない産院がある
私のいた産院では持ち込んだ器具の消毒ができなかったので、自分の搾乳器を使うことはできませんでした。
私のいた産院では、搾乳器を借りることもできませんでした。
出産直後の貴重な母乳ではありますが、病院のハンドソープなどで洗った自分の搾乳器で搾って、そのまま捨ててもよかったのかもしれません。

当時はそのアイデアを思いつきませんでした。
「ちょっと理系な育児」を読んでいたため、たくさん搾乳したいと思った私は、手だけで必死に搾乳することになりました。
退院後から搾乳器を使用し始める
手絞りには限界がありますので、退院後は搾乳器をつかいました。
絶対に直母に移行したいと考えた私は、高性能な電動搾乳器「スイング」を購入しました。
少しずつ搾乳量は増えていきました。
貯まった母乳を排出しないと新しい母乳は作られない
母乳を作る能力を高めるためには、おっぱいの中にある腺房をなるべくたくさん使うことが肝心です。
腺房に母乳が溜まっていると炎症の原因になりますし、新しい母乳づくりが止まってしまう仕組みになっています。
ですから、腺房をたくさん使うためには、頻繁に溜まった母乳を出す必要があります。
社会復帰しても授乳し続けるなら搾乳が必要

ちなみに、社会復帰してからもしばらく母乳をあげたい場合は、出社中にも時間をみつけて搾乳をする必要があります。
日本の会社でも女性の搾乳に配慮するところが増えてきていますが、私の会社にはそういった部屋や設備はありませんでした。
私は、午前と午後に1回ずつ会社ちかくの多機能トイレで搾乳して、そのまま捨てるサイクルを続けました。

メデラの搾乳機は社会復帰後も重宝しました。
母乳をうまく排出するためのマッサージ
出産直後は乳管が開通していないので、母乳の排出がスムーズにできません。
乳管を開通させるためには、赤ちゃんに乳首を吸ってもらうか、マッサージを施す必要があります。
退院後は、母乳外来の助産師に、マッサージをたくさんしてもらいました。
搾乳をしていて腱鞘炎になった場合の対策とは
私の赤ちゃんの場合、生まれて1ヶ月してからようやく直母練習ができるようになりました。
2ヶ月で安定して直母できるようになりましたが、それまでずっと搾乳に追われ、腱鞘炎をわずらいました。
直母になったのに腱鞘炎はなおらず、プロテインによる対策をとりました。
直母の訓練で赤ちゃんの乳頭混乱を克服

次は、赤ちゃんの直母の訓練について説明します。
赤ちゃんは、哺乳瓶の乳首に慣れてしまうと、直母ができなくなります。

吸えば出てくる、という感覚を失ってしまうようです。
先ほどご紹介した「ちょっと理系な育児」という本では、この現象を「乳頭混乱」と呼んでいます。
乳頭混乱を克服するための母乳相談室という名前の乳首
乳頭混乱を克服したいときに活躍するのが、ピジョンの「母乳相談室」という哺乳瓶の乳首です。

ピジョン 母乳相談室 哺乳びん SSサイズ乳首付(Amazon)
乳首単体で売られていて、ピジョンの哺乳瓶であればどのサイズでも取り付けられます。

SSサイズ 1個入 ピジョン 母乳相談室 乳首(Amazon)
この乳首に変更すると、赤ちゃんは、一生懸命吸わなければミルクが飲めないので、直母に似た状況をつくることができます。
母乳相談室を使うと直母の練習になるので、哺乳瓶から直母にスムーズにかえることができます。
乳頭混乱を克服するグッズは店頭に無く、ネット通販でしか買えなかった
この記事を書いている時点で、乳頭混乱を克服するためのグッズは、母乳相談室の乳首しか出ていないようです。
また、母乳相談室は店頭であまり見かけません。

私の実家周辺ではネット通販でないと手に入らない状況でした。
「乳頭混乱」という概念がもっと世に広まれば、様々な克服グッズが出てくるのではないかと思います。
母乳相談室の乳首で直母への移行に成功
私の赤ちゃんも、乳頭混乱に陥っていたようで、いきなり直母を練習してもうまくいきませんでした。
そこで、母乳相談室を使うことにしました。

洗浄して使い回すために、3つ購入しました。
生後1ヶ月になってから、授乳のはじめに毎回装着して飲ませはじめたところ、1週間ほどでうまく母乳相談室からミルクを飲めるようになりました。
すぐさま、直母練習を開始。
その後3週間で搾乳が不要になりました。
母乳相談室は使い続ける必要がある
私の場合、入院中の搾乳量が足りなかったためか、直母完全移行後も、母乳は必要量の半分しか出ませんでした。
残りを粉ミルクで補うにあたって「母乳相談室」を使い続けました。
ちなみに、8ヶ月で保育園に入ると保育園の哺乳瓶を使用させられましたが、乳頭混乱は起こりませんでした。
出産直後から搾乳をしておけば後で母乳量は増えていく

出産3日後から搾乳を開始した私の場合、搾乳期間中の母乳量は退院直前に1回あたりたったの35mlほどだったのが、徐々に増えて直母練習直前では70mlほどになりました。
そして、赤ちゃんが直母をできるようになると、飛躍的に母乳量が増え、会社に復帰するころには1回あたり130mlほど搾乳で得られるようになりました。
直母できないでいる間の搾乳量だけを見て、途中であきらめる必要はないということを後で身をもって知りました。
直母を目指した経緯を記したブログのもくじ
というわけで、出産から2ヶ月間の授乳にまつわることをまとめてみました。
出産直後から赤ちゃんの退院まで
退院までに揃えた授乳グッズ
退院直後から母乳外来に通う
退院から1週間目
子育て経験のある友人からアドバイスをもらう
退院から2週間目
腱鞘炎対策を考える
退院から3週間目
退院から4週間目
退院から7週間目
母乳育児がおわってPMS対策するなら
ムダ毛対策でリフレッシュのススメ
さいごに
産後は寝不足になりますし、ホルモンの作用による苛立ちもあります。その上、第一子の場合は、不慣れな子育てで諸々不安を抱えることになります。
私の場合、母乳量が増えずに途方に暮れていたとき、他の方はどんな感じなんだろう、途中から頑張って、どの程度母乳は増えるんだろう、といった情報がほしかったのを覚えています。
私の経験談や数値が、新たな生命を授かった方々の子育ての一助になれば幸いです。




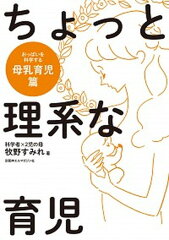








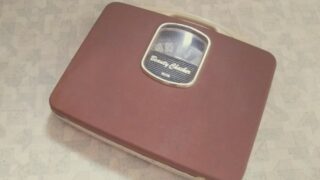


コメント