ノンタンシリーズは後半も充実
ノンタンあそぼうよ全23作品のうち、前半10作品を以下の記事でご紹介しました。
引き続き、後半の13作品をご紹介します。
※当ブログでは、最初の6年間に出版された10作品を「前半」の作品、それ以降を「後半」の作品と呼ぶことにしています。
- 後半作品の特徴と前半との違い
- ノンタンあそぼうよ後半13作品の詳細レビュー (1986年〜2019年)
- ノンタンぱっぱらぱなし(1986年8月)
- ノンタンこちょこちょこちょ(1987年11月)
- ノンタンバースデイブック(1987年12月)
- ノンタンおばけむらめいろ(1991年2月)
- ノンタンしゃっくりひっくひく(1996年7月)
- ノンタンいもうといいな(2001年6月)
- ノンタンいたいのとんでけ〜☆(2004年2月)
- ノンタンふわふわタータン(2005年10月)
- ノンタンでかでかありがとう(2006年6月)
- ノンタンおたのしみブック(2008年7月)
- ノンタンスプーンたんたんたん(2011年6月)
- ノンタンピクニックららら(2016年9月)
- ノンタンたいそう1・2・3(2019年4月)
- ノンタンあそぼうよシリーズ後半作品の魅力とシリーズ全体について
- さいごに
後半作品の特徴と前半との違い
後半のノンタンは、テイストが少し違います。
前半と後半で感じた違い

私の感じた違いを挙げるとすると、以下の通りです。
- ノンタンシリーズの主な変化
-
- 同じような言葉が繰り返される、単調な構成が多い
- 迷路やクイズなどの遊び要素が多用されている
- 絵のタッチが変わり、線が大味になり背景が簡素化
- 漫画のコマ割りのような表現が導入された
- 妹の「タータン」が登場し、兄妹の関係性が描かれる
- 前半の世界観や設定が覆されている部分がある
最初は前半との違いに戸惑いましたが、読み返すうちに後半ならではの魅力も発見できました。
後半作品の難易度と対象年齢

後半の絵本は、迷路やクイズなど知育要素が強くなり、全体的に難易度が上がっています。
特に「バースデーブック」「おたのしみブック」「おばけむらめいろ」などは、3歳以降でないと十分に楽しめない内容です。
1〜2歳の子供には、ストーリー性のある前半の作品から始めることをおすすめします。
ノンタンあそぼうよ後半13作品の詳細レビュー
(1986年〜2019年)
では、1冊ずつシリーズ後半のノンタンをご紹介します。
ノンタンぱっぱらぱなし(1986年8月)
片付けが苦手なノンタンは、みんなに「いーけないんだ いけないんだ!」と注意されても知らんぷり。
しかし、紙くずやゴミくずに好かれてつきまとわれ、ついに掃除・片付けをすることになります。
- 特徴・見どころ
-
- おもちゃや工作物が細かく描かれ楽しめる
- 散らかった部屋がリアルに描写されている
- ゴミが生き物のように動き出す、楽しい演出
- 片付けをすることの大切さを楽しく学べる
子供の反応・読み聞かせポイント
子供は掃除も遊びの延長として楽しんでくれます。
我が家では子供用の短いクイックルワイパーとお風呂モップを用意し、ノンタンの真似をして掃除することを促しています。
「ゴミくずさんがついてくるよ〜」と言うと、慌てて片付け始めます。
ノンタンこちょこちょこちょ(1987年11月)
お昼寝中に猫じゃらしでくすぐられて起きたノンタンは、お昼ご飯中のみんなを次々にくすぐりに行きます。
最後はみんなでくすぐりっこ大会になります。
- 特徴・見どころ
-
- 身近な植物である猫じゃらしが登場
- くすぐりっこをする楽しさが伝わってくる
- こちょこちょ、などのオノマトペが豊富
- 平和でほのぼのとしたストーリーが展開される
子供の反応・読み聞かせポイント
この絵本を読んでから、散歩中に猫じゃらしを欲しがるようになりました。
立派な穂をつけた猫じゃらしを一本折って持たせると、絵本のノンタンのように友達をくすぐろうとします。
読み聞かせ中も実際にくすぐると大喜びです。
ノンタンバースデイブック(1987年12月)
読者の子供宛に、ノンタンから不思議な卵がプレゼントされます。
逃げ出した卵を追いかけるノンタンと一緒に、特別な誕生日の冒険が始まります。
- 特徴・見どころ
-
- 名前・身長・体重を書き込める、参加型の絵本
- 手形を押すページがあり、成長を記録できる
- 付属のシールで、自分だけの作品をつくれる
- 世界に一つだけの特別な絵本になる
子供の反応・読み聞かせポイント
3歳以降の文字が少しわかるようになった頃がベストタイミング。
我が家では付属シールを別の場所に貼ってしまい、あとで、こんなに素敵な内容だとわかっていたらと後悔しました。
誕生日プレゼントと一緒に渡すと特別感が増します。
ノンタンおばけむらめいろ(1991年2月)
おばけむらの探検に出かけたノンタンたち。
みんなは怖がりますが、ノンタンだけは強がっておばけと仲良くなろうとします。
迷路を進みながら冒険が続きます。
- 特徴・見どころ
-
- 全てのページに迷路がある、遊び心のある構成
- おばけのデザインが可愛らしく安心して楽しめる
- あっかんべーのモチーフが随所に散りばめられている
- 怖いものを乗り越える勇気を育むきっかけになる
子供の反応・読み聞かせポイント
2歳ではまだ迷路は解けませんが、この絵本は大好きです。
おばけを怖がった時は「ノンタンみたいにおばけと友達になろう」と励ましています。
指でなぞりながら一緒に道を探すと、少しずつ迷路の概念を理解し始めます。
ノンタンしゃっくりひっくひく(1996年7月)
しゃっくりが始まったノンタンから、次々にみんなに感染していきます。
止めるために様々な方法を試しますが、最後にかえるさんが現れて意外な展開に。
- 特徴・見どころ
-
- しゃっくりを止める様々な民間療法が描かれる
- ひっくひっくのリズムが楽しい
- 逆立ちなど、体を動かす遊びの様子も描かれている
- アリの細かい描写も、見どころの一つ
子供の反応・読み聞かせポイント
「ひっく ひっく しゃっくり ひっく」を読むと本当にしゃっくりが出そうになります。
逆立ちの場面では必ず「やって!」とリクエストされ、逆さまにしてあげると大喜び。
焼き芋を拾うありを見つけて「ありさんラッキー!」と指摘する観察力も育ちます。
ノンタンいもうといいな(2001年6月)
うまくみんなと遊べない妹タータンを追い払ったノンタン。
しかしタータンがいなくなってしまい、みんなで探すことに。
ぶたさんが兄妹ならではの遊びを提案します。
- 特徴・見どころ
-
- 妹の「タータン」が初めて登場
- 兄妹ならではの複雑な感情がリアルに描かれる
- 漫画のコマ割りのような表現が導入される
- 物語を通して、兄妹愛の大切さが伝わってくる
子供の反応・読み聞かせポイント
タータンがノンタンの後ろに隠れる時、ガニ股になるノンタンを見て「歩けないよ」と心配していました(笑)。
「いいこと いいこと ないしょ ないしょ」のフレーズは、秘密の合言葉として実生活でも使えます。
ノンタンいたいのとんでけ〜☆(2004年2月)
車の遊具から追い出したタータンが転んで怪我をします。
ノンタンのおまじないで「いたいの」が飛んでいきますが、それが集まって「いたいのかいじゅう」になってしまいます。
- 特徴・見どころ
-
- ケガをしたときの痛みを和らげる、おまじないがテーマ
- 「いたいのかいじゅう」が想像力をかき立てる
- 作者の30年にわたる構想を経て生まれた作品
- 兄妹が仲直りをするシーンは、感動的な展開
子供の反応・読み聞かせポイント
空のいたいのかいじゅうが襲ってこないか、毎回ハラハラしながら聞いています。
実際に怪我をした時は「いたいのかいじゅうのところに飛んでけ〜」とおまじない。
キヨノサチコさんが長年温めた作品だけあって、深みがあります。
ノンタンふわふわタータン(2005年10月)
散歩中にノンタンに置いていかれたタータンは、ペンギンさんと出会い、風船を使って空の散歩を楽しみます。
タータンが主人公の特別な一冊。
- 特徴・見どころ
-
- 妹のタータンが主人公となる、珍しい作品
- ページをめくると、ペンギンがサプライズで登場
- カラフルな風船が登場する、華やかな場面が魅力
- 表紙の裏にも物語の続きが描かれている
子供の反応・読み聞かせポイント
子供は、茂みに隠れているペンギンさんを見つけて「ここにいる!」と大興奮。
風船がたくさん出てくる終盤は特に人気です。
表紙裏の絵でペンギンさんのその後が分かる仕掛けも、子供と一緒に発見する楽しみがあります。
ノンタンでかでかありがとう(2006年6月)
地面のお絵かきをタータンに邪魔されたノンタンは山の上へ移動。
しかしタータンには、ノンタンに見せたい素敵なサプライズがありました。
- 特徴・見どころ
-
- お絵かきをすることの楽しさが伝わってくる
- 逆さまの絵など、別の角度から見る工夫を促される
- 大声を出す前に深呼吸をする様子が印象的
- 感謝の気持ちを伝える大切さを学ぶことができる
子供の反応・読み聞かせポイント
でかでかノンタンとタータンの絵は逆さまなので、絵本を回転させて見せます。
「おえかき おえかき わーい わーい」はリズミカルで楽しく読めます。
大声を出す前の深呼吸は、子供と一緒にやると盛り上がります。
ノンタンおたのしみブック(2008年7月)
さがしっこ遊び、まねっこ遊び、あてっこ遊び、絵手紙、迷路、ぬりえなど、様々な遊びが詰まった参加型の絵本。
書き込みもできる特別な一冊。
- 特徴・見どころ
-
- 迷路や探し絵など、多様な遊び要素が満載
- 書き込みができる参加型で、自分だけの特別な絵本となる
- キヨノサチコさんの遺作で、ファンにとって特別な一冊
- さまざまな仕掛けがあるため、長く楽しむことができる
子供の反応・読み聞かせポイント
3歳頃が最も楽しめる内容で、プレゼントにも最適です。
長時間の移動や病院の待ち時間に大活躍。
キヨノサチコさんの最後の作品であり、ノンタンへの愛情が詰まっています。
ノンタンスプーンたんたんたん(2011年6月)
不思議なスプーンで何でも美味しく食べていたノンタンは、どんどん巨大化。
お星様やお月様まで食べ、お日様を味見しようとして叱られます。
- 特徴・見どころ
-
- たくさんの食べ物の名前が登場し、語彙力が高まる
- 空腹から、大きな冒険が始まり、想像力を刺激される
- 様々な食べ物が描かれているため、食育にも活用できる
子供の反応・読み聞かせポイント
食べ物の名前が出るたびに「これ!」と絵の中から探して指差します。
突拍子もない展開に、読んでいる大人は驚かされますが、子供は素直に楽しんでいます。
好き嫌いのある子への食育にも効果的です。
ノンタンピクニックららら(2016年9月)
ノンタンが運転するバスでみんなでピクニックへ。
お弁当広場、果物の木、お菓子の草むらを巡りながら、迷路を通って進む冒険。
- 特徴・見どころ
-
- バスの運転手という、子供たちの憧れの要素が描かれる
- たくさんの食べ物が登場し、楽しく読み聞かせできる
- 迷路の要素も含まれており、知育効果あり
- 1991年に出版された作品を、現代向けにアレンジ
子供の反応・読み聞かせポイント
好きな食べ物を見つけて大興奮、「これ食べたい!」と次々に指差します。
バスの運転手になったつもりで、ハンドルを握る真似をしながら読むと盛り上がります。
迷路は指でなぞりながら一緒に進みます。
ノンタンたいそう1・2・3(2019年4月)
みんなと一緒に楽しく体操ができる絵本。
様々な動きを真似しながら、数も覚えられる構成。
歌の楽譜付きでより楽しめます。
- 特徴・見どころ
-
- 体を動かしながら楽しめる、体操の絵本
- 数えながら体操をするので、数字の学習になる
- 楽譜が付いており、歌いながら体操ができる
- 人気の「ノンタンげんきげんき」から独立させた作品
子供の反応・読み聞かせポイント
実際に体を動かしながら読む参加型絵本。
「1・2・3」のリズムに合わせて体操すると、自然に数も覚えます。
雨の日の室内遊びにも最適。親子で一緒に体操すると絆も深まります。
ノンタンあそぼうよシリーズ後半作品の魅力とシリーズ全体について

最初は前半との違いに戸惑いましたが、後半には後半の魅力があります。
- 後半の特におすすめ作品
-
- 「いもうといいな」: 兄妹ならではの複雑な感情の描写が秀逸
- 「いたいのとんでけ〜☆」: 作者によって長年温められた作品で、深いテーマが描かれる
- 「ふわふわタータン」: 妹のタータンが主役の作品で、特別感あり
- 「でかでかありがとう」: 感謝の気持ちを学ぶことができる、心温まる内容
ノンタンあそぼうよシリーズ全体を通じた特徴
ノンタンあそぼうよシリーズは、対象年齢3歳からとされていますが、1歳からでも読み聞かせができる絵本だと私は感じています。
ノンタンは以下の普遍的な魅力があります。
- ノンタンの普遍的な魅力
-
- 豊かな表情と感情表現: ノンタンの喜怒哀楽が豊かに描かれており、子供たちの共感を呼ぶ
- 黒い輪郭線と原色の分かりやすい色使い: はっきりとした線と色は、幼い子供でも絵を認識しやすい
- オノマトペの効果的な使用: 「ぶーぶー」「ひっくひっく」といった擬音語や擬態語が豊富で、言葉のリズム感を楽しみながら読み進められる
- 子供の興味を的確に捉えたテーマ: 友達との遊びや生活習慣、冒険など、子供が夢中になるテーマが盛り込まれている
以上の特徴を網羅したノンタンは、認知力を高めるために最適な絵本です。
発達途上の1歳児からでも十分楽しんでもらえます。
ノンタンとミッフィーを比較

ノンタンは、よくミッフィーのシリーズと比較されます。
ノンタンは具体的で分かりやすい表現が特徴で、1歳から楽しめます。
一方、ミッフィーは言葉が洗練され絵が抽象的なため、2歳頃から楽しめるようになる、より高度な絵本と言えるでしょう。
さいごに
幼い頃からノンタンが大好きだった私としては、子供たちがノンタンの作品にたくさん触れて、それぞれの成長段階に合わせて楽しんでもらえることを願っています。
前半・後半それぞれに魅力があり、全23巻を通じて子供の成長を見守ってくれる素晴らしいシリーズです。

ぜひ、ノンタンを読み聞かせてあげてください。




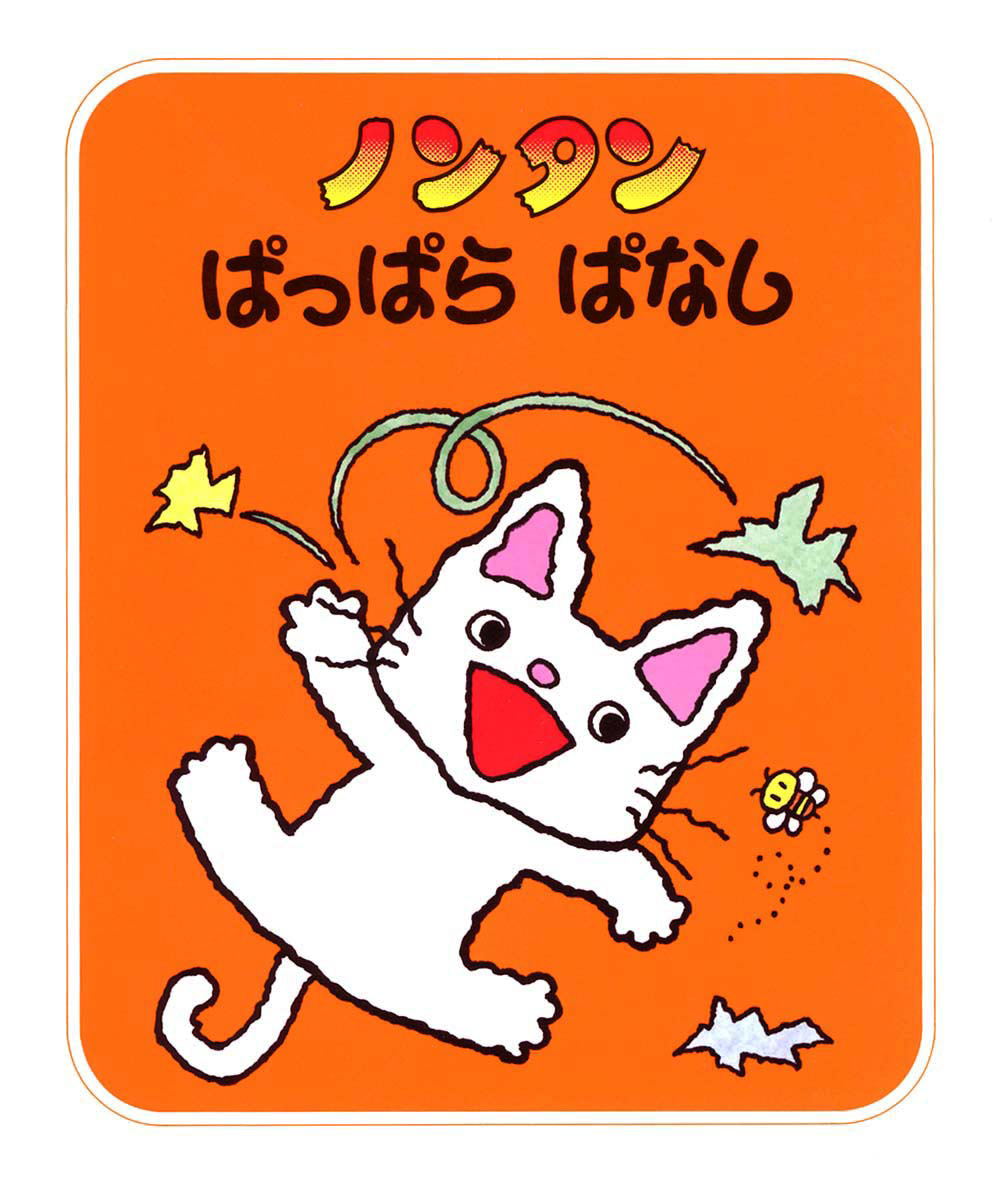









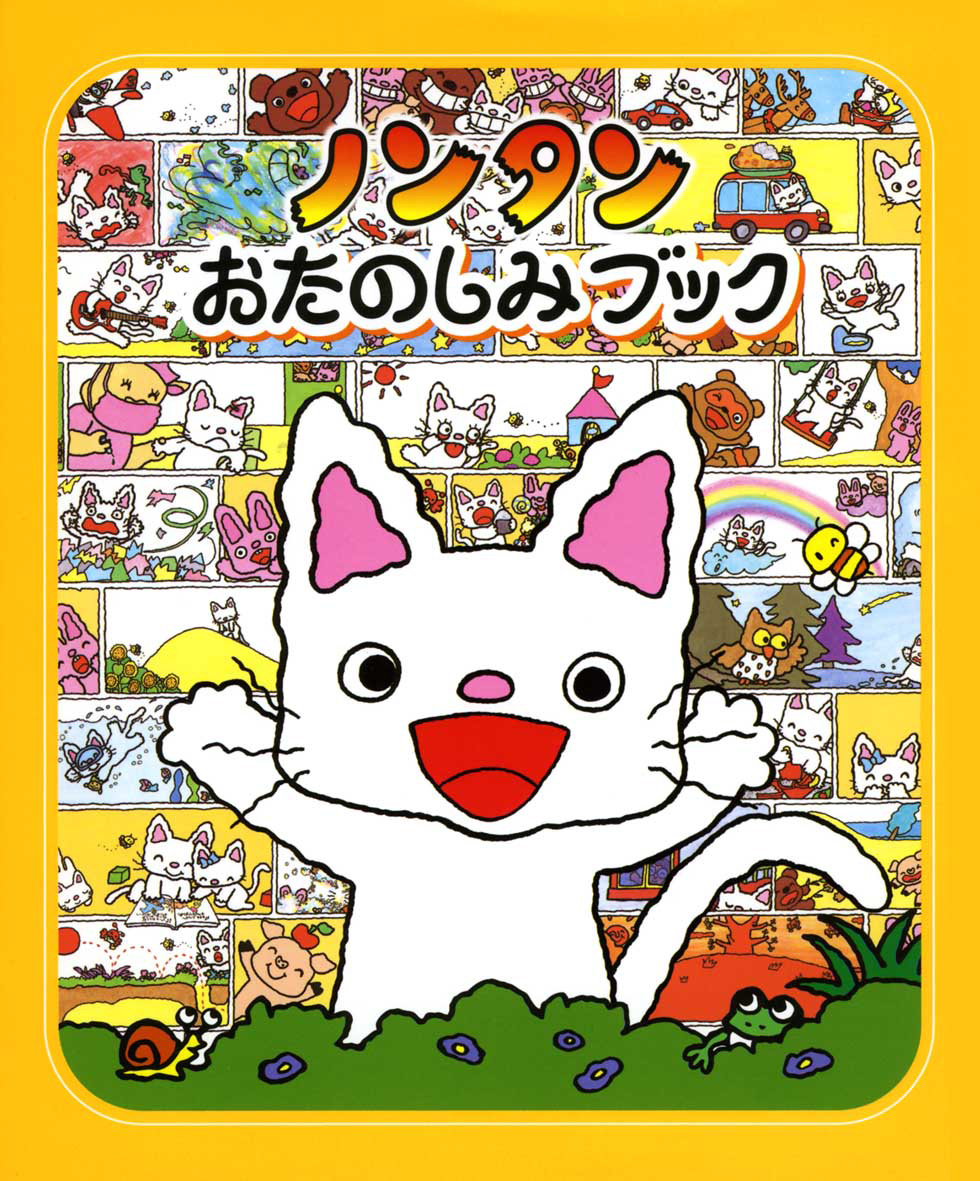





コメント